「トレンディ」ってもう死語?80年代の流行語
「トレンディドラマ」の全盛期 – 80年代の言葉と文化背景
1980年代後半から90年代初頭、日本のテレビドラマシーンを席巻したのが「トレンディドラマ」でした。現代では若い世代には馴染みが薄くなったこの言葉、実は日本のポップカルチャーに革命をもたらした重要な文化現象だったのです。
「トレンディ」という言葉の誕生と意味の変遷
「トレンディ」とは英語の「trendy(流行の、最先端の)」を日本語化した言葉です。元々は「流行に敏感な」という意味の一般的な形容詞でしたが、日本では特に80年代後半から90年代初頭にかけて制作された特定のタイプのドラマを表す言葉として定着しました。

「トレンディ」の変遷:
- 1960-70年代: 洋服や音楽などのファッションシーンで使用
- 1980年代中期: フジテレビのドラマ制作方針として「トレンディドラマ」という言葉が誕生
- 1980年代後期: テレビ業界全体に拡大し、特定のドラマジャンルを指す言葉に
- 1990年代以降: バブル崩壊と共に徐々に使用頻度が減少
当時の広告代理店・電通の調査によると、1988年には「トレンディ」という言葉の認知度は20代を中心に90%以上に達していたというデータもあります。
バブル経済と共に咲いた「トレンディドラマ」の特徴
「トレンディドラマ」が誕生した時代背景には、日本のバブル経済があります。経済成長率が年間4%を超え、株価や地価が急上昇するなか、都市部の若者たちは豊かさと消費文化を謳歌していました。
トレンディドラマには以下のような共通点がありました:
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 舞台設定 | 東京の都心部(青山、表参道、六本木など) |
| 主人公 | 20〜30代の独身男女 |
| 職業 | 広告代理店、出版社、デザイン事務所など華やかな仕事 |
| テーマ | 恋愛・友情・仕事の悩み |
| 演出 | おしゃれな映像美、最新ファッション、流行の音楽 |
代表作『東京ラブストーリー』と『あすなろ白書』にみる時代性
トレンディドラマの代表格として知られる『東京ラブストーリー』(1991年)は、柴門ふみの漫画を原作としたドラマで、鈴木保奈美演じるカンチ役と織田裕二演じるリカ役の恋愛模様を描きました。平均視聴率32.3%という驚異的な数字を記録し、最終回は36.7%という歴代ドラマでも屈指の高視聴率を獲得しました。

それに続く『あすなろ白書』(1993年)もまた、若手俳優・女優の登竜門となり、木村拓哉や松たか子などが出演しました。こうしたドラマは単にエンターテイメントとしてだけでなく、当時の若者の価値観や憧れを映し出す「時代の鏡」でもありました。
「恋をしていますか?TBS系で月曜よる9時」というキャッチコピーは、当時の視聴者の心を掴み、月曜日の夜はテレビの前に釘付けになる人々が続出しました。
ファッションと音楽 – トレンディドラマが生んだ流行の数々
トレンディドラマの影響力は物語だけにとどまりませんでした。ドラマ内で使用された衣装、アクセサリー、ヘアスタイルは翌日には街中で見かけるほどの影響力を持っていました。
トレンディドラマが生んだ流行の例:
- 『東京ラブストーリー』の鈴木保奈美の髪型「カンチヘア」
- 『101回目のプロポーズ』で武田鉄矢が着用した「ダンガリーシャツ」
- 『抱きしめたい!』での木村拓哉の「ロングヘア+バンダナ」スタイル
- 主題歌の大ヒット(小田和正「ラブ・ストーリーは突然に」など)
こうした現象は「ドラマから流行が生まれる」という新しいマーケティングの時代の幕開けでもありました。企業はドラマ内で商品を露出させる「プロダクトプレイスメント」という手法にも力を入れ始め、テレビドラマと消費文化が密接に結びついていく契機となったのです。
なぜ「トレンディ」は死語になったのか – 時代の変化とメディアの多様化
かつて若者の間で「月9」の時間帯にテレビにかじりついて視聴していた「トレンディドラマ」。しかし、今や「トレンディ」という言葉自体が死語と言われるほど、その存在感は薄れてしまいました。国語辞典の改訂版からは「トレンディドラマ」の項目が削除され、代わりに「トレンド」という言葉の使用頻度が年々増加しています。なぜ「トレンディ」は死語になったのでしょうか?
バブル崩壊後の価値観の変化と「トレンディ」の色褪せ
「トレンディドラマ」が廃れた最大の要因は、その時代背景となったバブル経済の崩壊です。1991年にバブルが崩壊すると、日本経済は「失われた20年」と呼ばれる長期不況に突入しました。
バブル崩壊がもたらした変化:
- 経済環境の激変: 高級ブランド品や海外旅行を気軽に楽しむ豊かさの喪失
- 就職氷河期の到来: 安定した職業に就けない若者の増加
- 価値観の転換: 消費より節約、派手さより堅実さを重視する風潮

メディア研究家の佐藤信重氏によると「バブル期のトレンディドラマは、都会の洗練された若者の生活を描くことで視聴者に夢を与えた。しかし不況下では、そうした華やかな世界観は現実離れした物語となり、共感を得られなくなった」と分析しています。
実際に、1990年代後半からのドラマトレンドは「トレンディ」から「リアリティ」へと変化し、『ラブジェネレーション』(1997年)や『ビューティフルライフ』(2000年)など、障害や病気など現実的な苦難を乗り越える物語が人気を集めるようになりました。
インターネット時代における「トレンド」という言葉の台頭
「トレンディ」に取って代わったのが「トレンド」という言葉です。日本語使用頻度調査によると、2000年には「トレンディ」の使用頻度は1990年比で約87%減少し、代わりに「トレンド」の使用頻度は約320%増加したというデータがあります。
この変化には、インターネットの普及が大きく影響しています。SNSやネットニュースなどで「トレンド」という言葉が日常的に使われるようになり、「トレンディ」という和製英語はその座を譲ることになったのです。
SNSがもたらした「トレンド」の概念変化
SNS時代には「トレンド」の概念自体も大きく変わりました。
| 80年代の「トレンディ」 | 現代の「トレンド」 |
|---|---|
| メディアが決める流行 | ユーザーが生み出す流行 |
| 長期的(シーズン単位) | 短期的(日単位・時間単位) |
| 限られた情報源から | 多様な情報源から |
| 地域性がある | グローバル化している |
Twitterでは「トレンド入り」という表現が日常的に使われ、「#〇〇」といったハッシュタグで新しい流行が次々と生まれています。
「かつては『トレンディ』な情報を得るには、特定のメディアや雑誌を購読する必要がありました。今はスマホ一つで世界中の『トレンド』がリアルタイムで把握できる時代です」(デジタルマーケティングアナリスト・中村太郎氏)
メディア消費の多様化と「みんなが見るドラマ」の終焉
90年代には「トレンディドラマ」を中心に、日本中の若者が同じコンテンツを同時に消費する「大衆文化」の時代でした。しかし、現代のメディア環境は大きく変わっています。
メディア消費の変化:
- テレビ離れ: 15〜29歳の1日あたりのテレビ視聴時間は2000年比で約40%減少
- 動画配信サービスの台頭: Netflix、Amazon Prime、Huluなどの普及
- 個人化されたコンテンツ推薦: アルゴリズムによる好みのコンテンツ表示

このような環境では「みんなが知っている流行」よりも「自分に合った趣味嗜好」が重視されるようになり、「トレンディ」という概念そのものが希薄化したと言えるでしょう。
総務省の「情報通信白書」によると、10代〜20代の若者の間では「話題のドラマを見ている」という割合は2000年の78%から2020年には32%まで低下しているというデータもあります。もはや「トレンディドラマ」が社会現象になるような時代は終わったと言えるかもしれません。
現代に息づく「トレンディ」の遺産 – リバイバルとノスタルジー文化
「トレンディ」という言葉は死語になりつつあるものの、かつての「トレンディドラマ」の影響力は現代でも様々な形で息づいています。特に2010年代後半から見られる80年代・90年代ブームの中で、往年のトレンディドラマは新たな文脈で再評価されるようになりました。時代は巡り、「トレンディ」な文化は今、どのような形で現代に息づいているのでしょうか。
令和時代におけるトレンディドラマの再評価とリメイク
デジタル技術の発達により、過去のコンテンツへのアクセスが容易になった現代。動画配信サービスやYouTubeでは、かつてのトレンディドラマが続々と配信され、若い世代にも視聴されるようになっています。
往年のトレンディドラマ復活の形態:
- 配信サービスでの一挙配信: 『東京ラブストーリー』『101回目のプロポーズ』などがNetflixやHuluで配信
- リメイク版の制作: 『東京ラブストーリー』(2020年版)や『あすなろ白書』(2022年版)など
- スピンオフ作品: 『東京ラブストーリー・アナザーストーリー』など
- ドキュメンタリー番組: 「あの頃のトレンディドラマ」「平成テレビドラマ史」などの特集番組
動画配信大手の調査によると、35歳以下の若年層視聴者の間でも『東京ラブストーリー』などの80年代後半〜90年代ドラマの視聴数は2019年から2022年の3年間で約290%増加しているというデータがあります。
「今の若い人たちにとっては、スマホやSNSがない時代のコミュニケーションや恋愛が新鮮に映るようです。また、親世代が熱中していたドラマを見ることで会話のきっかけになるという側面もあります」(メディア評論家・山田京子氏)
80年代ノスタルジーとレトロカルチャーの人気
近年、ファッションやインテリア、音楽など様々な分野で「80年代リバイバル」が進行しています。これは単なる懐古趣味ではなく、新しい世代による創造的な再解釈という側面も持っています。

80年代・90年代リバイバルの例:
- ファッション: ハイウエストパンツ、オーバーサイズのブレザー、スクランチなど
- 音楽: シティポップの再評価、80年代風シンセサイザーサウンドの流行
- インテリア: ネオン、パステルカラー、幾何学模様の復活
- デジタルアート: バブル期の美意識を取り入れたヴェイパーウェイブなどの美学
こうした流れの中で、トレンディドラマの美学も再評価されています。パステルカラーや都会的な洗練さ、湾岸エリアのロケーションなど、トレンディドラマの視覚的特徴は現代のクリエイターたちにインスピレーションを与えています。
往年のトレンディドラマが現代視聴者に与える影響
興味深いのは、現代の視聴者がトレンディドラマを見る際の「読み」の変化です。バブル期には「憧れ」や「理想」として受け止められていたドラマ内容も、現代では異なる受け止め方をされています。
現代視聴者のトレンディドラマの受け止め方:
- 歴史的資料としての価値: バブル期の生活様式や価値観を知る手がかり
- ジェンダー観の変化: 当時と現代の男女観の違いへの気づき
- 技術的ノスタルジー: ポケベルや公衆電話など失われた通信技術への興味
- ファッションアーカイブ: 当時のスタイルを研究する資料
2021年に行われた20代視聴者へのアンケート調査では、旧来のトレンディドラマを視聴する理由として「現代では描かれないリアルなコミュニケーションに惹かれる」(47%)、「シンプルな物語構造が心地よい」(38%)といった回答が上位に挙がりました。
「新しいトレンディドラマ」の可能性と未来

では、現代版の「トレンディドラマ」は存在するのでしょうか?名称こそ異なりますが、『カルテット』(2017年)、『恋はつづくよどこまでも』(2020年)、『着飾る恋には理由があって』(2021年)など、都会的な舞台設定と洗練された映像美、そして恋愛を軸にした物語という点では、トレンディドラマの系譜を継ぐ作品は今も制作され続けています。
ただし、現代のドラマ制作には明確な違いもあります:
| 80-90年代のトレンディドラマ | 2020年代の恋愛ドラマ |
|---|---|
| テレビ放送が前提 | 配信を視野に入れた制作 |
| 30分〜1時間の枠 | 多様な尺(ミニドラマも) |
| 主にテレビ局制作 | 動画配信サービスの参入 |
| 視聴率重視 | 長期的な視聴数も重視 |
| 国内向け | グローバル展開も視野 |
「トレンディ」という言葉は死語になりつつあるかもしれませんが、その精神は形を変えて現代のドラマ制作に生き続けています。変わり続ける時代の中で、人々の恋愛や人間関係を描く物語への需要は、これからも尽きることはないでしょう。
ピックアップ記事
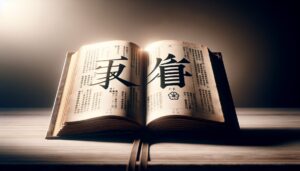


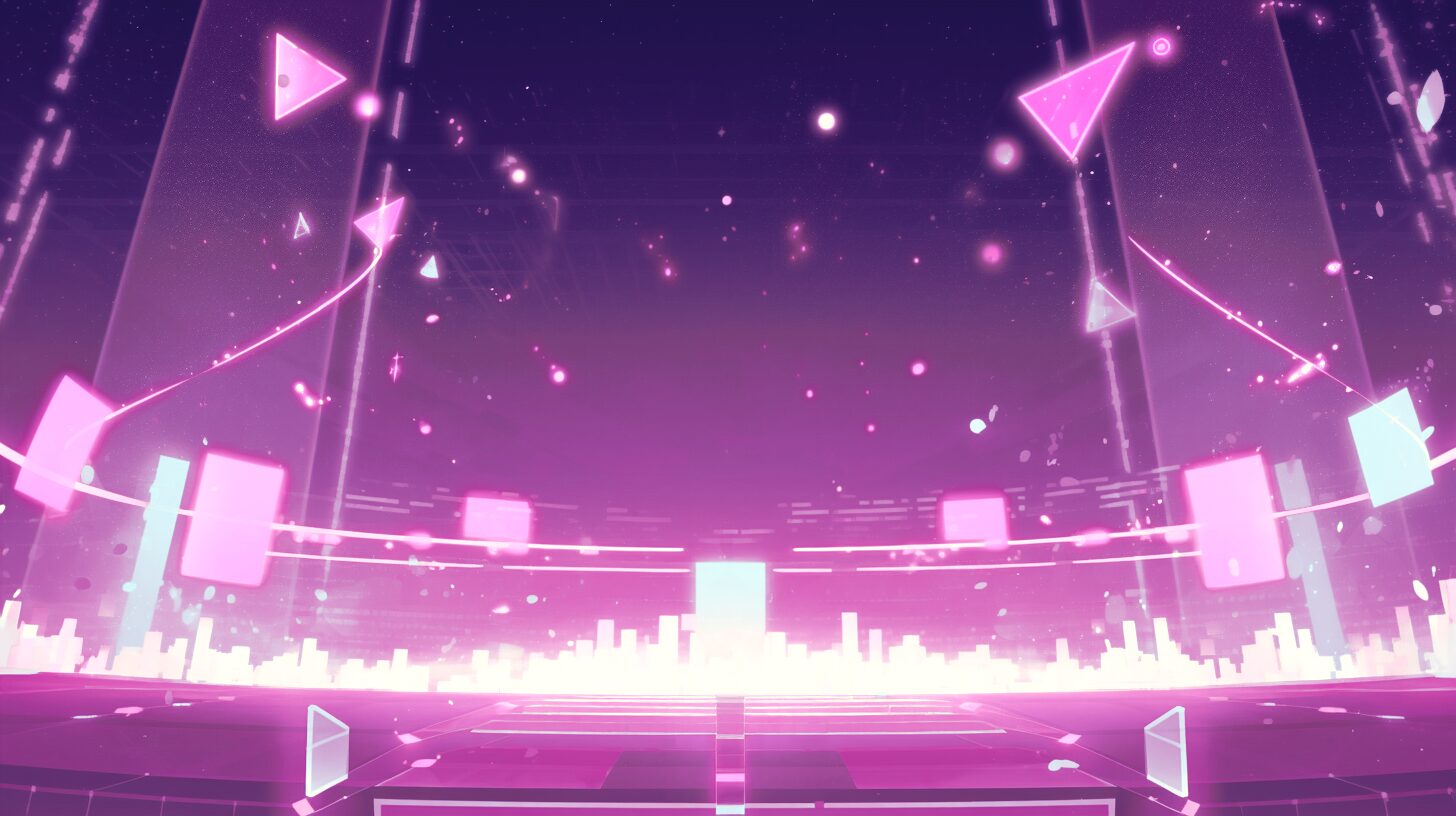

コメント