バブル時代を彩った「ワンレン」と「ボディコン」の登場背景
1980年代後半から1990年代初頭、日本は「バブル景気」と呼ばれる空前の好景気に沸いていました。土地価格は高騰し、株価は上昇の一途をたどり、「土地神話」なる言葉も生まれるほど。この経済的な豊かさは、当時の人々のライフスタイルやファッションにも大きな影響を与えました。特に女性のファッションやヘアスタイルの世界では、「ワンレン」と「ボディコン」という二つのキーワードが時代を象徴する存在となりました。
経済状況がファッションに与えた影響
バブル期の日本では、「消費は美徳」とも言われるほど、消費活動が活発化しました。特に若い女性たちの消費意欲は旺盛で、ブランド品や高級アイテムへの投資を惜しまない風潮がありました。

当時の経済指標を見てみると:
| 年代 | 日本のGDP成長率 | ファッション・美容関連支出(対前年比) |
|---|---|---|
| 1986年 | 2.9% | +7.8% |
| 1987年 | 4.2% | +12.3% |
| 1988年 | 6.8% | +18.7% |
| 1989年 | 5.3% | +15.2% |
| 1990年 | 5.2% | +8.6% |
(※データは経済企画庁「国民生活白書」より引用)
この経済的な余裕が、「見た目に投資する」という文化を生み出し、美容院での施術やファッションアイテムへの出費が増加。特にOLと呼ばれる女性たちは、給料の多くを自己投資に回し、「ワンレンヘア」や「ボディコンドレス」を取り入れることで、自身のステータスを表現していました。
1980年代の日本人女性の社会的地位の変化
バブル時代は、女性の社会進出が進み始めた時期でもありました。1986年に施行された「男女雇用機会均等法」によって、職場での女性の地位にも変化が現れ始めます。しかし、実質的にはまだ「お茶くみ」や「受付」といった補助的な役割が多く、キャリア形成の壁は高いものでした。
そんな中、仕事帰りに楽しむディスコやクラブでの時間は、女性たちにとって自己表現の場となっていきました。
OL文化とファッション

OLの一日のスケジュール(1980年代後半)
- 朝7:30 – 出勤前に美容院でスタイリング
- 9:00-17:30 – オフィスワーク
- 18:00-19:30 – 同僚との軽い飲み会
- 20:00-22:00 – ディスコやクラブへ
平日のこうしたスケジュールをこなすOLたちは、ワンレンヘアのような手入れが比較的簡単で、かつスタイリッシュなヘアスタイルを好み、オフィスからそのままクラブに行けるようなボディコンドレスを着用することも。昼と夜の顔を使い分ける「24時間戦える女性」が一つの理想像になっていきました。
海外セレブの影響
バブル期は、海外への旅行や留学も増え、国際的な視野が広がった時期でもありました。特にアメリカやヨーロッパのセレブリティの影響は大きく、マドンナやシンディ・クロフォードなどのファッションアイコンが日本の女性たちに大きな影響を与えました。
マドンナの『マテリアル・ガール』(1985年)のミュージックビデオでの衣装は、日本でも大きな話題となり、ボディコンスタイルの普及に一役買いました。また、映画『フラッシュダンス』(1983年)の主人公のファッションも、タイトなシルエットを強調するスタイルとして取り入れられていきました。
こうした海外からの影響と、日本特有の経済状況や社会背景が組み合わさり、「ワンレン」と「ボディコン」という、バブル時代を象徴するファッション用語が生まれ、広まっていったのです。
「ワンレン」ヘアスタイルの特徴と流行の軌跡
バブル期のファッションシーンを語る上で欠かせないのが「ワンレン」というヘアスタイル。当時の街を歩けば、多くの女性たちがこのスタイルを取り入れていました。しかし「ワンレン」とは具体的にどのようなヘアスタイルだったのでしょうか?その特徴と流行の背景に迫ります。
ワンレンヘアの定義と技術的特徴
「ワンレン」とは、髪の長さを全体的に一定の長さ(One Length)に揃えたヘアスタイルのこと。具体的には以下のような特徴を持っています:
- 均一の長さ – 前髪から後ろ髪まで、一直線に切り揃えられている
- シャープな輪郭 – 特に襟足や顔周りのラインが直線的
- ボリューム感 – トップにボリュームを持たせたスタイリングが一般的
- 艶やか – ストレートパーマやトリートメントで艶を出すことが重要

技術的には、当時発展してきたストレートパーマ技術や、セニングという間引きテクニックを使わない「ブロッキング」という手法が用いられました。これにより、髪に重さと艶を持たせることができたのです。
ワンレンの一番の特徴は、その シンプルさの中にある洗練された印象 にありました。過度な装飾や複雑なカットを排し、直線的なラインだけで構成されるこのスタイルは、当時の「シンプル・イズ・ベスト」という価値観を体現していたとも言えるでしょう。
当時の人気ヘアスタイリストと雑誌の影響力
バブル期のヘアスタイルの流行には、著名なスタイリストの存在が欠かせませんでした。特に以下のスタイリストたちがワンレンヘアの普及に大きく貢献しています:
- 佐藤志明 – 「SHIMA」サロンの創始者で、直線的なカットの第一人者
- 山本哲也 – 「PEEK-A-BOO」を設立し、「シンプル・イズ・ベスト」を掲げる
- 三科光平 – 「mod’s hair」日本支社の中心人物
これらのスタイリストたちの作品は、当時絶大な人気を誇った美容雑誌を通じて広く伝わりました。特に『an・an』『non-no』『JJ』といった女性誌は、ワンレンヘアを特集する記事を頻繁に掲載。これらの雑誌の発行部数は以下のように推移しています:
| 雑誌名 | 1985年 | 1988年 | 1991年 |
|---|---|---|---|
| an・an | 65万部 | 78万部 | 85万部 |
| non-no | 72万部 | 88万部 | 96万部 |
| JJ | 51万部 | 69万部 | 78万部 |
(※日本雑誌協会データより推計)
有名人がもたらしたワンレンブーム
ワンレンヘアを一気に広めたのは、以下のような当時の人気タレントたちでした:
- 中山美穂 – 1987年頃からワンレンボブを取り入れ、「ミポリン」の愛称で親しまれた
- 南野陽子 – 艶やかなストレートのワンレンで「ナンノ」として人気を博す
- 工藤静香 – やや長めのワンレンヘアを活かしたダンスパフォーマンスで注目を集める
特に中山美穂の髪型は「ミポリンカット」と呼ばれ、美容室でのオーダー率ナンバーワンになったとも言われています。当時の統計によれば、1988年に都内の美容室で最も多かったオーダーの約35%がワンレンヘアだったというデータもあります。
ワンレンのバリエーションと進化

単一のスタイルと思われがちなワンレンですが、実はバブル期を通じて様々なバリエーションが生まれました:
- ショートワンレン – 耳が見える長さの短めスタイル(1987年頃~)
- ミディアムワンレン – 肩につくか触れないかの長さ(1988年~1990年が最盛期)
- ロングワンレン – 肩甲骨あたりまでの長さ(1989年~1991年に人気)
- インナーワンレン – 表面は段差をつけ、内側をワンレンにするスタイル(1990年代初頭)
特に1990年に入ると、単調になりがちなワンレンに変化をつけるため、前髪だけパーマをかけたり、部分的にレイヤーを入れたりするアレンジも登場。こうした進化形も含め、ワンレンヘアは約5年間にわたって日本女性の髪型の主流であり続けました。
「ボディコン」ファッションの魅力と社会現象
「ボディコン」という言葉を聞くと、多くの人がバブル時代の象徴として思い浮かべるのではないでしょうか。体にぴったりとフィットするドレスやスカートは、当時の女性たちの自信と解放感を表現する手段として大流行しました。では、このファッションはどのように生まれ、どのような社会現象を巻き起こしたのでしょうか。
ボディコンの起源と定義
「ボディコン」とは「Body Conscious」の略語で、文字通り「身体を意識した」という意味です。体の曲線に沿うようにぴったりとフィットするデザインが特徴で、主に以下のような要素を持っています:
- 伸縮性のある素材 – スパンデックスやライクラなどの弾力性のある生地を使用
- タイトなシルエット – 特にウエストからヒップにかけてのラインを強調
- 適度な丈感 – 膝丈からミニまで、脚のラインも見せるデザイン
- 鮮やかな色使い – ビビッドカラーや蛍光色などの目を引く色彩
ボディコンという用語自体は、実は1985年頃からアメリカのファッション業界で使われ始めていたものが日本に輸入された形です。日本での普及は1987年頃から始まり、1989年から1991年にかけて最盛期を迎えました。
ファッション史研究家の村田裕子氏によれば、「ボディコンは単なるファッションアイテムではなく、女性の社会的地位向上や経済力の表現としての側面も持っていた」と分析しています。実際、当時の調査では、ボディコンを着用する女性の約65%が「自信が持てる」と回答していたというデータもあります。
デザイナーたちが生み出したボディコンの代表的スタイル
ボディコンブームを牽引したのは、以下のようなブランドやデザイナーたちでした:
- アズディン・アライア – チュニジア出身のデザイナーで「ボディコンの父」とも呼ばれる
- エルヴェ・レジェ – 「バンデージドレス」と呼ばれる独自のテクニックで人気を博す
- ジャンニ・ヴェルサーチ – 大胆なカットと鮮やかな色使いで知られる

日本国内では以下のようなブランドが人気を集めました:
| ブランド名 | 代表的アイテム | 価格帯(当時) |
|---|---|---|
| BODY DRESSING | ワンピースドレス | 15,000〜25,000円 |
| ROPÉ | タイトスカート | 12,000〜18,000円 |
| KRISEMARE | ツーピースセット | 20,000〜35,000円 |
| Miss Chloe | ストレッチドレス | 25,000〜40,000円 |
これらのブランドは渋谷や原宿の百貨店、セレクトショップで展開され、仕事帰りのOLたちで連日賑わいました。特に1989年の調査では、20代後半から30代前半の働く女性の約40%が「ボディコン系アイテムを1着以上持っている」と回答するほどの普及率でした。
ボディコンを着こなすためのアイテムたち
ボディコンファッションは単にドレスやスカートだけでなく、トータルコーディネートとして楽しまれていました。特に以下のようなアイテムが必須とされていました:
- パンプス – 特に9〜12cmのヒールが定番
- ボディスーツ – 下着のラインを見せないための必須アイテム
- 太ベルト – ウエストマークを強調するアクセサリー
- ショルダーパッド – 肩幅を強調し、ウエストを相対的に細く見せる工夫
また、当時のファッション雑誌『JJ』の調査によれば、ボディコンを着こなすために、以下のようなボディメイクも人気がありました:
ボディコン時代の人気エクササイズ
- エアロビクス(週1〜2回・約65%の女性が実践)
- ジェーン・フォンダの「ワークアウト」(自宅で・約42%)
- 腹筋トレーニング(毎日・約38%)
ディスコやクラブシーンとの関連性

ボディコンファッションが最も映えるのは、やはりナイトシーンでした。1980年代後半、東京を中心に全国の主要都市では多くのディスコやクラブが営業していました。代表的な場所としては:
- ジュリアナ東京(港区六本木)- 1991年に開店し、「ジュリアナ系」という派生ファッションも生み出す
- マハラジャ(渋谷・大阪・名古屋など)- 全国展開したディスコチェーン
- ゴールドクレスト(銀座)- より大人向けの高級クラブ
これらの場所では、ボディコンドレスを着た女性たちが自由に踊り、当時流行した「タイガー&ドラゴン」や「ハレハレ踊り」などのダンスを楽しんでいました。特にジュリアナ東京では、「ジュリアナ民」と呼ばれるボディコンファッションの極形とも言えるスタイルが生まれ、バブル末期のファッションシーンを象徴する存在となりました。
ボディコンファッションは、このように単なる衣服の流行を超えて、女性のライフスタイルや価値観を表現する社会現象として、バブル時代の日本に深く根付いたのです。
ピックアップ記事
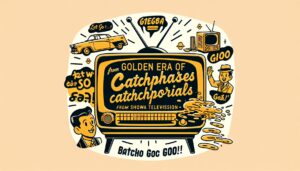




コメント