「いただきます」の意味と歴史的背景
私たちが当たり前のように口にしている「いただきます」という言葉。毎日の食事の前に自然と言っている方も多いでしょうが、この短い言葉には深い意味と長い歴史が込められています。一体いつから日本人は食事の前にこの言葉を言うようになったのでしょうか?
「いただく」という言葉の語源と変遷
「いただきます」の語源となる「いただく」は、元々は物理的に「頭上に載せる」という意味を持っていました。神仏に供物を捧げる際、頭上に持ち上げる動作から来ているとされています。これが時代とともに「上位の者から物を受け取る」という敬意を表す意味へと変化していきました。

食事に関して言えば、「命をいただく」という意味合いが強く、食材となる動植物の命に対する感謝や、食事を用意してくれた人への感謝を込めた言葉なのです。
「いただく」の意味の変遷:
- 古代:物理的に頭上に載せる行為
- 中世:神仏に捧げる敬虔な行為
- 近世以降:敬意を表して受け取る行為
- 現代:感謝の気持ちを表す日常的な挨拶
仏教の影響と「五観の偈」との関係
「いただきます」という習慣には、仏教の教えが大きく影響しています。特に禅宗の食事作法である「五観の偈(ごかんのげ)」との関連が指摘されています。
「五観の偈」とは、食事の前に唱える以下の5つの観念です:
- 功の多少を計り彼の来処を量る(食べ物がどれだけの労力で得られたかを考える)
- 己が徳行の有無を忖り、供に応ず(自分の行いが食べ物をいただくにふさわしいかを反省する)
- 心を防ぎ過患を離るるは貪等を宗とす(むさぼりなどの心の過ちを慎む)
- 正に良薬を事とするは形を持するが為なり(良薬として食事をとり、体を維持する)
- 道業を成ぜんが為に、この食を受く(修行を完成させるためにこの食事をいただく)
この教えが一般庶民にも広がり、簡略化されて「いただきます」という言葉に集約されていったという説があります。
江戸時代から現代までの使われ方の変化
江戸時代の文献では、食事の前に「南無三宝(なむさんぼう)」と唱えたり、「手を合わせる」という記述は見られますが、「いただきます」という言葉そのものの記録は少ないようです。
現代のような形で「いただきます」が広く定着したのは、明治以降とされています。特に学校教育の中で食事のマナーとして教えられるようになったことが大きな要因です。
| 時代 | 食事前の一般的な挨拶 |
|---|---|
| 平安時代 | 特定の言葉は記録されていない |
| 鎌倉~室町時代 | 武家では「恐れながら」などの言葉も |
| 江戸時代 | 「南無三宝」「手を合わせる」など |
| 明治以降 | 「いただきます」が徐々に定着 |
| 昭和 | 学校教育を通じて全国的に普及 |
世界の食事前の挨拶との比較

日本の「いただきます」に相当する食事前の挨拶は、世界各国でも見られます。しかし、その内容や意味合いは文化によって異なります。
- フランス:「Bon appétit(ボナペティ)」(良い食欲を)
- イタリア:「Buon appetito(ブオン・アペティート)」(良い食欲を)
- ドイツ:「Guten Appetit(グーテン・アペティート)」(良い食欲を)
- 英語圏:「Enjoy your meal(食事を楽しんで)」
- イスラム圏:「Bismillah(ビスミッラー)」(神の名において)
- ユダヤ教:食前のパンに対する祝福「ハモツィ」
これらと比較すると、日本の「いただきます」には「食材となった命への感謝」という独特の要素が含まれています。食物連鎖の中で生かされているという認識や、自然への畏敬の念が込められている点が特徴的です。
このように「いただきます」という一言には、日本人の自然観や倫理観、感謝の精神が凝縮されているのです。日常的に使う言葉だからこそ、その意味を時々思い返してみると、食事の時間がより豊かなものになるかもしれませんね。
「ごちそうさま」の由来と文化的意義
食事を終えた後に言う「ごちそうさま」。この言葉もまた、日本の食文化に深く根付いた独特の挨拶です。「いただきます」とセットで使われることが多いこの言葉には、どのような歴史と意味が込められているのでしょうか。
「ご馳走」という言葉の成り立ち
「ごちそうさま」の「ごちそう」は「馳走(ちそう)」に丁寧さを表す接頭語「ご」がついたものです。現代では豪華な食事を指す言葉として使われていますが、元々はまったく異なる意味を持っていました。
「馳走」の漢字が持つ本来の意味
「馳走」という漢字をよく見てみると、「馳(はせる)」と「走(はしる)」という二つの漢字からできています。どちらも「走る」という意味を持つ漢字です。なぜ食事を意味する言葉に「走る」が二つも使われているのでしょうか?
「馳走」の字義的意味:
- 「馳」:馬を走らせる、急ぐ
- 「走」:走る、駆ける
- 合わせて「馳走」:走り回る、奔走する
つまり、「馳走」は本来「走り回る」という動作を表す言葉だったのです。
「走り回る」からの意味の発展
では、どのようにして「走り回る」が「食事」を意味するようになったのでしょうか?
これは、客人をもてなすために主人が食材を調達したり料理を準備したりと、あちこち走り回る様子を表していたと考えられています。つまり、「ごちそうさま」の本来の意味は「あなたが私のために走り回ってくださったことに感謝します」ということなのです。

この言葉の変遷を時系列でまとめると:
- 平安時代:「馳走」は「走り回る」という動詞として使用
- 室町時代:「客人をもてなすために走り回る」という意味合いが強まる
- 江戸時代:「馳走」=「もてなしの料理」という意味が定着
- 現代:豪華な食事全般を「ごちそう」と呼ぶようになる
江戸時代の随筆『醒睡笑(せいすいしょう)』には、「馳走とは、走り馳せ候なり」(馳走とは、走り回ることである)という記述があり、当時の認識を知ることができます。
感謝の表現としての文化的背景
「ごちそうさま」という言葉には、単に食事への感謝だけでなく、日本文化に根付いた多層的な感謝の念が込められています。
「ごちそうさま」に込められた感謝の対象:
- 食事を用意してくれた人への感謝
- 食材となった生き物への感謝
- 食材を育てた自然への感謝
- 食に関わるすべての人々への感謝
特に日本の伝統的な考え方では、「いのち」を「いただく」という意識が強く、「ごちそうさま」には食物連鎖の中で生かされている私たちの命への感謝も含まれています。
仏教の影響も見逃せません。「五観の偈」を唱えて食事を始め、食後には「済んだ」ことを表す作法がありました。これが一般に広まり、簡略化されて「ごちそうさま」になったという側面もあります。
地域による言い回しの違いと特徴
「ごちそうさま」は全国共通語として使われていますが、地域によって異なる言い回しも存在します。
地域別の「ごちそうさま」表現:
- 東北地方:「おしまい」「すみました」
- 関西地方:「ごっつぉうさん」「おおきに」
- 九州地方:「ごちそうさん」「ごちそうさんでした」
- 沖縄:「くわっちーさびたん」(ごちそうさまでした)
また、「ごちそうさま」と「ごちそうさまでした」の使い分けも興味深いポイントです。家庭内では略式の「ごちそうさま」を使うことが多い一方、他家や飲食店では丁寧な「ごちそうさまでした」を使う傾向があります。
| 場面 | 一般的な言い方 |
|---|---|
| 家庭内 | 「ごちそうさま」 |
| 友人宅 | 「ごちそうさま」「ごちそうさまでした」 |
| 目上の人宅 | 「ごちそうさまでした」 |
| 飲食店 | 「ごちそうさまでした」 |

このように「ごちそうさま」という言葉は、単なる食事の締めくくりの挨拶ではなく、日本人の人間関係や自然との関わり方、感謝の精神を反映した文化的に豊かな表現なのです。普段何気なく使っている言葉ですが、その歴史と意味を知ると、日々の食事がより特別なものに感じられるのではないでしょうか。
現代社会における「いただきます」と「ごちそうさま」の価値
スマホを片手に一人で食事をする光景が珍しくなくなった現代。昔ながらの食事の挨拶である「いただきます」と「ごちそうさま」の習慣は、どのように受け継がれ、どのような価値を持っているのでしょうか。時代が変わっても色あせない、これらの言葉の現代的意義について考えてみましょう。
食育における二つの言葉の重要性
2005年に「食育基本法」が制定されて以降、日本では食育が国の重要政策として位置づけられています。その中で「いただきます」「ごちそうさま」という言葉は、食育の重要な要素として再評価されています。
文部科学省の食育推進基本計画では、「食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力の育成」の一環として、これらの挨拶の習慣化を推奨しています。単なるマナーとしてではなく、食に関わる人々への感謝や自然の恵みへの畏敬の念を育む機会として重視されているのです。
食育における「いただきます」「ごちそうさま」の位置づけ:
- 食べ物への感謝の気持ちを育む
- 食事を作ってくれた人への敬意を表す
- 命の大切さや食物連鎖への理解を深める
- 共食の喜びを体験する機会とする
- 日本の食文化を継承する
学校教育での教え方と実践例
学校給食の時間は、「いただきます」「ごちそうさま」の意味を学ぶ絶好の機会となっています。多くの小学校では、単に言葉を唱えるだけでなく、その背景にある意味や価値についても指導が行われています。
学校給食における実践例:
- 給食当番の活動を通して、食事の準備の大変さを実感する
- 生産者や調理員への感謝の気持ちを手紙にしたためる
- 「いただきます」を言う前に、その日の給食の食材や調理法について学ぶ時間を設ける
- 食材の生産過程を学ぶ校外学習(農業体験など)と関連づける
文部科学省が2019年に発表した調査によると、小学校の99.8%が給食時に「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶を実施していると報告されています。学校教育を通じて、これらの言葉の習慣は確実に次世代に継承されているといえるでしょう。
家庭での継承と課題
一方、家庭での「いただきます」「ごちそうさま」の実践には、いくつかの課題も見られます。
国民生活センターが2018年に実施した調査では、家庭で毎食「いただきます」を言う習慣がある家庭は約76%、「ごちそうさま」は約71%という結果が出ています。概ね定着しているものの、以下のような課題も指摘されています:
- 個食化(家族がバラバラの時間に食事をとる現象)の増加
- スマホ等を見ながらの食事による挨拶の省略
- 共働き世帯の増加による家族揃っての食事機会の減少
- 言葉の形式的な継承(意味を理解せずに言う)

これらの課題に対して、「ファミリー食育」を推進する動きも見られます。例えば、週末だけでも家族で食卓を囲む「ウィークエンド共食」の奨励や、食材の買い物から調理まで家族で行うことで、食への感謝の気持ちを育む取り組みなどです。
国際化する日本における文化継承の意義
近年、日本を訪れる外国人観光客や在住外国人が増加する中で、「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶は、日本文化を象徴する要素として注目されています。
訪日外国人向けのガイドブックやブログでは、しばしばこれらの挨拶が日本の食文化体験の一部として紹介されています。また、日本料理店のスタッフが外国人客に対してこの習慣を説明する場面も増えています。
国際交流における「いただきます」「ごちそうさま」の役割:
- 日本の食文化や価値観を伝える窓口となる
- 異なる文化を持つ人々との相互理解の糸口となる
- 言語を超えて共有できる食事の儀式として機能する
- 日本人のアイデンティティを再確認する機会となる
外国人留学生を対象とした2020年の調査では、「日本で最も印象に残った食習慣」として「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶が最も多く挙げられました。食べ物や命に対する敬意を表す文化として、多くの外国人にポジティブに受け止められているようです。
デジタル時代における食事の挨拶の変容と本質
SNSの普及により、食事の写真をアップする前に「いただきます」とコメントをつける習慣や、テイクアウト食品の画像に「ごちそうさまでした」とハッシュタグをつける現象も見られるようになりました。
このような新しい形の「いただきます」「ごちそうさま」に対しては賛否両論ありますが、デジタル空間においても食への感謝や敬意を表す文化が自然と生まれていることは興味深い現象です。

デジタル時代の「いただきます」「ごちそうさま」:
- SNS投稿での「#いただきます」「#ごちそうさまでした」の使用
- オンライン飲み会での食事前後の挨拶
- フードデリバリーサービスの普及による感謝の対象の拡大
- バーチャル料理教室での食事作法の継承
形は変われども、食べ物と食に関わる人々への感謝という本質は変わらないようです。時代に合わせて柔軟に形を変えながらも、その核心を保ち続ける日本の食文化の強さと柔軟性が感じられます。
このように「いただきます」「ごちそうさま」は、単なる形式的な挨拶を超えて、日本人の価値観や自然観、人間関係の築き方を象徴する重要な文化的要素なのです。デジタル化や国際化が進む中でも、その本質的な価値は色あせることなく、むしろ新たな意義を持って継承されていくのではないでしょうか。
ピックアップ記事
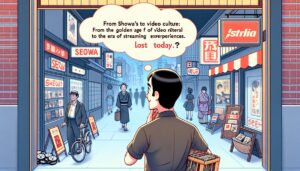




コメント