「女子大生」から「キャリアウーマン」へ:時代が映す女性呼称の変遷
日本社会の変化とともに、女性を表す言葉も大きく変わってきました。特に「女子大生」「OL」「キャリアウーマン」といった言葉は、単なる呼称を超えて、各時代の女性の社会的立場や価値観を映し出す鏡となっています。これらの女性呼称の変遷を辿ることで、日本における女性の社会進出の歴史と、それに伴う言語表現の移り変わりが見えてきます。
「女子大生」の誕生と社会的イメージ
「女子大生」という言葉が一般的に使われ始めたのは、高度経済成長期の1960年代から1970年代にかけてです。この時代、女性の大学進学率は急速に上昇し、1960年にはわずか2.5%だった女性の大学・短大進学率が、1975年には22.2%にまで上昇しました。
当初、「女子大生」は特別な存在として扱われ、ファッションリーダーやトレンドセッターとしての側面が強調されていました。「女子大生」という言葉には、教養があり、将来性があり、そして何より「モダン」であるという憧れのイメージが付与されていたのです。

しかし同時に、「女子大」という言葉には「お嬢様学校」「良妻賢母教育」といった伝統的な女性像も内包されており、進学しても最終的には結婚するという社会的期待も含まれていました。1970年代の女性雑誌では「女子大生の花嫁修業」といった特集が組まれることも少なくありませんでした。
「OL」文化の全盛期
「OL(オーエル)」は「Office Lady」の略で、1960年代後半から使われ始めた言葉です。それまでの「BG(ビージー:Business Girl)」や「事務員」に代わる新しい女性呼称として定着しました。
OLという言葉が最も輝いていたのは、バブル経済期の1980年代から1990年代初頭でしょう。この時代、OLは「働く女性」の代名詞となり、「OL市場」は企業にとって重要なターゲットとなりました。「OL流行語大賞」が創設されたのもこの時代です。
国立国語研究所の調査によれば、1980年代の女性向け雑誌では「OL」という言葉の使用頻度が「女子大生」の約3倍に達していました。OLファッション、OLグルメ、OL小説など、OLを冠した文化現象が次々と生まれました。
しかし、OLという言葉には「補助的業務」「結婚までの腰掛け」といったニュアンスも含まれており、キャリア志向の強い女性たちからは次第に違和感を持たれるようになっていきました。
「キャリアウーマン」の台頭
1985年の男女雇用機会均等法施行を背景に、「キャリアウーマン」という言葉が注目されるようになりました。それまでの「OL」とは一線を画す、専門職や管理職を目指す女性を表す言葉として使われ始めたのです。
「キャリアウーマン」という言葉には、単に「働く女性」という意味を超えて、「自立した女性」「プロフェッショナルな女性」というポジティブなイメージが込められていました。1990年代には、テレビドラマでもキャリアウーマンを主人公とした作品が多く制作されるようになりました。
しかし興味深いことに、「キャリアウーマン」という言葉自体は2000年代に入ると徐々に使用頻度が減少しています。Google Trendsのデータによれば、2004年から2020年にかけて「キャリアウーマン」の検索ボリュームは約70%減少しています。これは、女性の社会進出が当たり前になり、特別な呼称で区別する必要性が薄れてきたことの表れかもしれません。
現代では「女性起業家」「女性リーダー」など、より具体的な役割や職業を表す言葉が増え、単に性別で一括りにする女性呼称は減少傾向にあります。職業表現の変化は、社会における女性の立場の変化を如実に反映しているのです。
昭和の象徴「女子大生」:憧れと時代背景を探る

昭和30年代から40年代、「女子大生」という言葉は単なる女子学生を表す呼称を超え、一つの社会現象、憧れの象徴として日本社会に定着しました。この時代、高度経済成長とともに女性の高等教育への進学率が上昇し、「女子大生」は新しい時代の先駆者として注目を集めました。
「女子大生」誕生の社会的背景
昭和30年代、女性の大学進学率はわずか2.5%程度と非常に低く、大学に通う女性は極めて限られた存在でした。そのため「女子大生」は希少価値を持ち、教養と知性を備えた「新しい女性像」として注目されるようになりました。
当時の日本社会では、女性の理想的なライフコースは「良妻賢母」が主流でしたが、女子大生はその枠を超えた存在として認識されていました。彼女たちは従来の女性像とは異なる、知的で洗練された印象を持ち、ファッションリーダーとしても注目されていました。
特に昭和36年(1961年)に始まった『女子大生会館』というラジオ番組は、女子大生ブームに火をつけた象徴的な存在でした。この番組は深夜に放送され、リスナーからの相談に女子大生が答えるという斬新な形式で、多くの若者の支持を集めました。
メディアが作り上げた「女子大生」イメージ
「女子大生」という言葉の普及には、雑誌や映画などのメディアが大きく貢献しました。昭和30年代後半から40年代にかけて、「平凡パンチ」「週刊プレイボーイ」などの男性誌が「女子大生特集」を頻繁に組み、理想の女性像として女子大生を取り上げました。
1960年代の映画『キューティーハニー』シリーズや『女子大生シリーズ』などでは、明るく活発で知的な女子大生像が描かれ、大ヒットしました。これらの作品を通じて、「女子大生」は若さと知性を兼ね備えた理想的な女性像として定着していきました。
当時の女子大生を表す特徴的なファッションとしては:
– ミニスカート(1967年頃から流行)
– ボブヘア
– ローファーと靴下の組み合わせ
– トレンチコート
これらのアイテムは「女子大生ファッション」として広く認知され、女子大生でない若い女性たちにも影響を与えました。
「女子大生」言葉の社会的意味の変遷
昭和40年代に入ると、女性の大学進学率は徐々に上昇し、1970年(昭和45年)には6.5%に達しました。この頃から「女子大生」は単なる憧れの存在から、より身近な存在へと変化していきます。
同時に「女子大生」という言葉の持つ意味も微妙に変化していきました。初期の「知性と教養の象徴」というイメージから、「若さと自由の象徴」というイメージへとシフトしていったのです。
特に昭和40年代後半には、就職難の時代背景もあり、「女子大生」は「結婚までの腰掛け」という見方も広まりました。「女子大生」という言葉の職業表現としての側面が薄れ、一時的な状態を表す言葉としての性格が強まったのです。

この時代の求人広告では「女子大卒」という表現が使われ始め、企業が女性の高学歴を評価し始めたことを示しています。しかし、実際の職場では「お茶くみ」や「タイピスト」といった補助的な業務が中心で、キャリア形成の機会は限られていました。
データで見ると、1975年(昭和50年)の女性の大学・短大進学率は合わせて約30%に達し、「女子大生」は特別な存在ではなくなりつつありました。これにより、「女子大生」という言葉の持つ社会的インパクトは徐々に薄れていくことになります。
女性呼称変化の観点から見ると、「女子大生」から「OL(オフィスレディ)」へと社会の注目が移行していく過程は、日本社会における女性の位置づけの変化を如実に反映しています。教育機関から職場へ、そして「学ぶ存在」から「働く存在」へと、女性の社会的役割の重心が移動していったのです。
「OL」の誕生と定着:バブル期に咲いた女性職業表現の花
「OL」という言葉の誕生背景
「OL(オーエル)」という言葉は、英語の「Office Lady」の頭文字から生まれた和製英語です。1960年代後半から1970年代にかけて一般化し始め、バブル経済期の1980年代から1990年代初頭にかけて最も広く使われるようになりました。それまでの「BG(ビージー:Business Girl)」や「女事務員」という呼称に代わって登場したこの言葉は、高度経済成長期に女性の社会進出が進む中で生まれた新しい女性呼称でした。
当初は「オフィスレディー」と呼ばれることもありましたが、次第に「OL」という略称が定着していきました。この言葉が広く受け入れられた背景には、企業で働く女性たちの社会的な認知度が高まったことがあります。特筆すべきは、この言葉が単なる職業名称を超えて、一つのライフスタイルや文化を表す言葉へと発展していったことです。
バブル期のOL文化と社会現象
1980年代後半から1990年代初頭のバブル経済期、OLは日本の経済成長を支える重要な存在であると同時に、消費文化の主役としても注目されました。当時の調査によれば、20代OLの約65%が自分の収入の30%以上をファッションや娯楽に費やしていたというデータもあります。
バブル期のOL文化を特徴づけるものとして、以下のような現象がありました:
- 「OL市場」の誕生:企業がOLをターゲットにした商品開発やマーケティングを積極的に展開
- 「OL小説」の流行:田中康夫の『なんとなく、クリスタル』(1981年)を始めとするOLの生活を描いた小説が大ヒット
- ファッション雑誌の隆盛:『JJ』『CanCam』などOL向けファッション誌が部数を伸ばす
- 「OL腰痛」などの新語:デスクワークによる健康問題も社会的に認知
この時代、「OLといえば結婚までの腰掛け」という認識も強く残っていましたが、同時に「キャリアウーマン」という職業表現も登場し始め、女性の働き方に関する価値観が徐々に多様化していく過渡期でもありました。
OLの実像とメディア表象
バブル期のOLは、メディアでは「華やかで自由に消費を楽しむ女性たち」として描かれることが多かったものの、実際の職場では依然として「お茶くみ」「コピー取り」といった補助的な業務を担当することが多く、その実態には大きなギャップがありました。
1989年の調査では、大企業に勤めるOLの約78%が「将来のキャリアに不安を感じている」と回答し、華やかなイメージの裏側にある現実も浮き彫りになっていました。しかし同時に、この時代のOLたちは、それまでの世代と比べて高学歴化が進み、女子大生言葉の影響を受けた新しいコミュニケーションスタイルを職場にもたらす存在でもありました。
テレビドラマでは『男女7人夏物語』(1986年)や『東京ラブストーリー』(1991年)などが人気を博し、OLの恋愛や仕事の悩みが多くの視聴者の共感を呼びました。また、雑誌『hanako』(1988年創刊)は、グルメやレジャーを楽しむOLのライフスタイルを提案し、新たな女性呼称変化の象徴ともなりました。
バブル期に咲き誇ったOL文化は、日本の社会や経済が大きく変化する中で生まれた独特の現象でした。「OL」という言葉は単なる職業名称を超えて、一つの時代を象徴する文化的アイコンとなり、今日においても昭和後期から平成初期の日本社会を語る上で欠かせない職業表現として記憶されています。その後の女性の社会進出の変遷を理解する上でも、「OL」という言葉の持つ歴史的・文化的意義は非常に大きいと言えるでしょう。
「キャリアウーマン」の登場:女性の社会進出と言葉の力
バブル期に定着した「キャリアウーマン」という言葉

1980年代後半から90年代初頭にかけてのバブル経済期、日本社会に「キャリアウーマン」という言葉が広く浸透しました。それまでの「OL(オフィスレディ)」が一般職として補助的な業務を担う女性を指したのに対し、キャリアウーマンは管理職や専門職として活躍し、自らのキャリア形成に積極的な女性を表す言葉として使われるようになりました。
当時の雑誌『NIKKEI WOMAN』(1988年創刊)や『働く女性のためのBIGtomorrow』などが、このキャリアウーマン像を積極的に取り上げ、スーツにショルダーパッドを入れた「パワードレッシング」というファッションスタイルと共に、新しい女性像として提示していました。
「キャリアウーマン」が持つ二面性
「キャリアウーマン」という言葉は、女性の社会進出の象徴として肯定的に使われる一方で、時に「仕事一筋で冷たい」「結婚より仕事を優先する」といったステレオタイプを伴うこともありました。1991年に放送されたドラマ「東京ラブストーリー」の主人公・赤名リカは、まさにこの時代を象徴するキャリアウーマン像として描かれ、視聴率30%を超える人気を博しました。
興味深いのは、「キャリアウーマン」という呼称が男性側の視点から生まれた面があることです。「キャリアマン」という言葉がほとんど使われないことからも分かるように、男性の場合はキャリア志向が当然視される一方で、女性の場合は特別に名付ける必要があったという社会背景が浮かび上がります。
データで見る「キャリアウーマン」の時代
国立国語研究所の調査によると、「キャリアウーマン」という言葉の使用頻度は1986年から1992年にかけて急増し、その後徐々に減少していきました。これはバブル経済の推移とほぼ一致しています。
また、労働省(現・厚生労働省)の統計データによれば、1986年の男女雇用機会均等法施行後、女性の管理職比率は徐々に上昇し始めました。しかし1990年代初頭でも、課長相当職以上の女性比率はわずか2%程度に留まっていました。つまり「キャリアウーマン」という言葉が広まった時期は、実際の女性管理職はまだ非常に少なく、むしろ「これから増えていくだろう」という期待や予測を込めた言葉だったとも言えます。
「女性呼称変化」の中での位置づけ
「女子大生」「OL」から「キャリアウーマン」への職業表現の変遷は、単なる言葉の変化以上の意味を持っています。これは女性の社会的立場や期待される役割の変化を如実に反映しているのです。
特に注目すべきは、「女子大生」「OL」が若さや華やかさを強調する言葉であるのに対し、「キャリアウーマン」は能力や専門性を前面に出した表現であるという点です。この変化は、女性が「見られる存在」から「行動する主体」へと徐々に移行していく過程を言語面から捉えたものと言えるでしょう。
現代における「キャリアウーマン」という言葉
2000年代に入ると、「キャリアウーマン」という言葉の使用頻度は大きく減少しました。代わりに「ワーキングマザー」「女性管理職」「女性リーダー」といった、より具体的な役割や立場を表す言葉が増えてきています。
国立国会図書館のデジタルコレクションで「キャリアウーマン」をキーワードに含む文献数を調べると、1990年代には年間100件以上あったものが、2010年代には年間20件程度にまで減少しています。これは「キャリアウーマン」という特別な呼称が必要なくなってきた、つまり女性がキャリアを追求することが特別ではなくなってきた証拠とも解釈できます。
また、現代では「キャリアウーマン」という言葉自体が若干古めかしく感じられ、バブル期の遺物として捉えられることもあります。しかし、この言葉が果たした歴史的役割—女性のキャリア志向を可視化し、社会に定着させた功績—は決して小さくありません。
「女子大生」「OL」「キャリアウーマン」という女性呼称の変化は、日本社会における女性の立場の変遷を映し出す鏡であり、言葉の持つ社会的影響力を示す貴重な事例と言えるでしょう。
平成・令和の女性呼称:「就活生」から「ワーママ」まで
多様化する平成・令和の女性呼称

平成時代に入ると、バブル経済の崩壊とともに女性の社会的立場や役割にも大きな変化が訪れました。「OL」や「キャリアウーマン」といった昭和の女性呼称に代わり、より多様で細分化された呼び方が登場します。この変化は、女性のライフスタイルの多様化と、社会における女性の役割の拡大を如実に反映しています。
平成初期から中期にかけて広く使われるようになったのが「就活生」という言葉です。これは男女問わず使用される言葉ですが、特に女子大生の就職活動が一般化し、「就職氷河期」などの言葉とともに社会現象として注目されるようになりました。1990年代後半の調査によると、女子大生の約85%が卒業後の就職を希望するようになり、昭和時代の「花嫁修業としての女子大」というイメージは大きく変わりました。
「働く女性」の細分化と新たな呼称
平成時代中期から後期にかけて特徴的だったのは、働く女性を表す言葉がより細分化されたことです。
「ワーキングマザー」から「ワーママ」へ:1990年代に「ワーキングマザー」という言葉が定着し始め、2000年代に入ると略称の「ワーママ」が若い世代を中心に広く使われるようになりました。2018年の厚生労働省の調査では、子育て世代(25-44歳)の女性の就業率は76.5%に達し、「ワーママ」は特別な存在ではなく一般的な選択肢となりました。
「バリキャリ」の登場:「バリバリ働くキャリアウーマン」を略した「バリキャリ」という言葉は、2000年代に入って広く使われるようになりました。昭和時代の「キャリアウーマン」より強いニュアンスを持ち、仕事に対する積極的な姿勢を強調する呼称です。
「専業主婦」と「兼業主婦」:女性の働き方の多様化に伴い、「専業主婦」と「兼業主婦」という区別も一般化しました。特に「兼業主婦」は平成時代に入って広く使われるようになった言葉で、家事と仕事を両立する女性の増加を反映しています。
令和時代の新しい女性呼称
令和に入ると、働き方改革やテクノロジーの発展により、さらに新しい女性呼称が生まれています。
「リモートワーカー」「テレワーカー」:コロナ禍を契機に急速に広まった働き方で、特に育児中の女性にとって新たな選択肢となりました。2020年の調査では、女性テレワーカーの約65%が「育児との両立がしやすくなった」と回答しています。
「フリーランス女子」「ノマドワーカー」:特定の会社に属さず、自由な働き方を選択する女性を表す言葉として定着しつつあります。2021年の調査によると、女性フリーランスの数は5年間で約1.5倍に増加しました。

「ポートフォリオワーカー」:複数の仕事を組み合わせて収入を得る働き方を指す言葉で、令和時代の新しい女性の働き方を象徴しています。
女性呼称から見える社会の変化
「女子大生」から「OL」、「キャリアウーマン」を経て、「ワーママ」や「フリーランス女子」まで、女性呼称の変遷は日本社会における女性の立場や役割の変化を如実に反映しています。特に注目すべきは、現代の女性呼称が「働き方」や「ライフスタイル」によって細分化されている点です。これは女性の社会進出が一般化し、多様な選択肢が認められるようになった証と言えるでしょう。
また、「女子」という言葉が「OL」や「キャリアウーマン」といった職業表現から切り離され、「就活女子」「婚活女子」「アラサー女子」など年齢や活動に紐づく表現として使われるようになったことも特徴的です。
女性呼称の変化は単なる言葉の変遷ではなく、社会構造や価値観の変化を映し出す鏡です。これからも女性の社会的役割や立場の変化とともに、新たな女性呼称が生まれ続けることでしょう。
ピックアップ記事
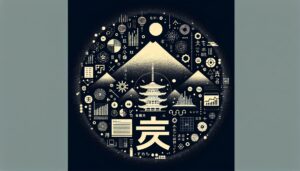


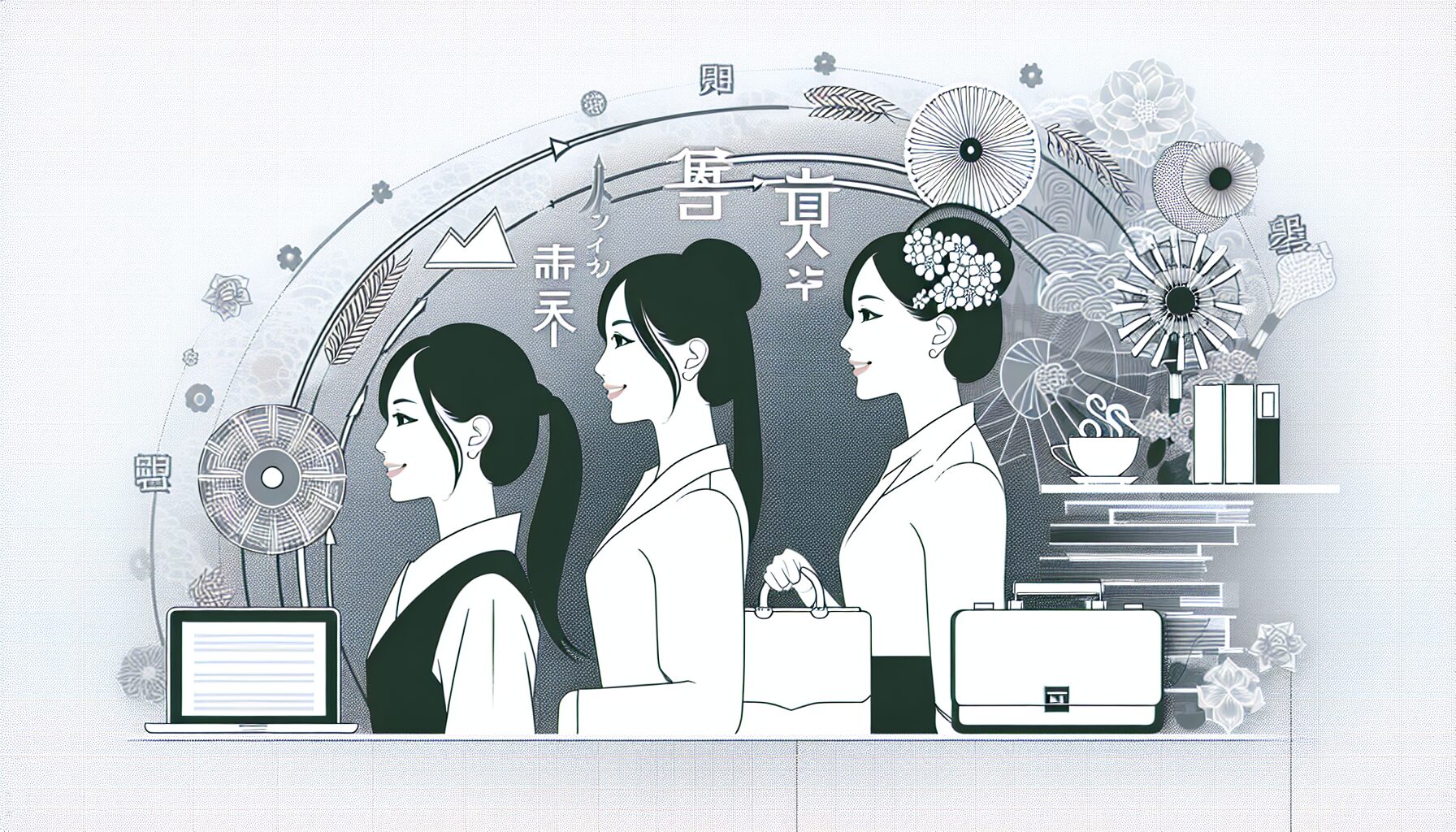

コメント