失われゆく日本の方言 – なぜ地域の言葉は消えていくのか
かつて日本全国には、地域ごとに独特の「言葉の色」がありました。「あずましい」(東北地方で「心地よい」の意)や「おおきに」(関西で「ありがとう」の意)など、地域の歴史や文化、自然環境を映し出す鏡のような存在が方言です。しかし近年、これらの方言は急速に姿を消しつつあります。国立国語研究所の調査によれば、若年層における伝統的方言の使用率は過去50年で約60%減少したというデータもあるほどです。
標準語の普及と方言の衰退
明治時代からの言語政策
方言が減少し始めた大きな転機は、明治時代にさかのぼります。1872年の学制発布以降、日本政府は国民統合のために「標準語」の普及を国策として推進しました。特に1902年に国語調査委員会が「口語法」を制定し、東京の山の手言葉をベースにした標準語が公式に定められたことは重要な転換点でした。
当時の教育現場では「方言札」と呼ばれる、方言を話した生徒に罰として首から下げさせる札が使われることもありました。山形県の古老の証言によれば、「学校さ行ぐど、方言喋っただけで、札かけらいで、恥ずかしくて泣いだもんだ」といった経験を持つ方も少なくありません。このような強制的な標準語化政策は、方言に対する劣等感を植え付ける結果となりました。
マスメディアの発達と言語の均質化

テレビやラジオなどのマスメディアの普及も、方言衰退の大きな要因です。1953年にテレビ放送が開始され、全国ネットの番組が増えるにつれ、日本全国どこでも同じ言葉が聞こえるようになりました。
メディアによる言語の均質化データ
| 年代 | 全国放送局数 | 方言番組の割合 | 若年層の方言使用率 |
|---|---|---|---|
| 1955年 | 16局 | 約23% | 約78% |
| 1975年 | 102局 | 約8% | 約51% |
| 1995年 | 127局 | 約3% | 約33% |
| 2020年 | 131局 | 約5% | 約22% |
出典:総務省「放送メディア白書」および国立国語研究所「言語生活調査」より筆者作成
現在ではインターネットの普及により、さらに言語の均質化が進んでいます。YouTubeやSNSなどのプラットフォームでは、全国どこでも通じる「ネット標準語」のような言葉が生まれ、地域差はますます小さくなっています。
現代社会における方言の位置づけ
方言コンプレックスから方言リバイバルへ
かつて「方言=田舎くさい、教養がない」というイメージが強く、多くの地方出身者は上京する際に必死で標準語を身につけようとしました。「方言矯正教室」なるものが東京で開かれ、地方出身の若者たちが通っていたという記録も残っています。
しかし1980年代頃から、このような方言に対する否定的な見方は徐々に変化し始めました。1989年の「方言ブーム」では、お笑い芸人による方言ネタが人気を集め、1996年には『釣りバカ日誌』などの映画やドラマでも方言が積極的に取り入れられるようになりました。
最近では「方言かわいい」文化も生まれ、若い女性を中心に地域の方言をファッション感覚で取り入れる動きも見られます。2019年の調査では、「方言を使いたい・残したい」と考える10代・20代が65%にのぼるという結果も出ています。
若者の方言離れの実態

しかし、方言への関心が高まる一方で、実際の若者の言葉からは伝統的な方言が急速に失われています。特に以下の特徴が顕著です:
- 理解はできるが使わない方言の増加:祖父母が使う方言を理解はできても、自分では使わない若者が増えています
- 方言の単語レベル化:文法や語尾などの体系的な方言は失われ、単語レベルでのみ方言が残る傾向
- 「新方言」の発生:伝統的方言と標準語が混ざった新しい言葉づかいの誕生
例えば、宮城県の若者調査(2018年)では、伝統的な方言表現「~さいん」(〜しない)を普段使うと答えた10代はわずか12%だったのに対し、新方言「~さない」を使うと答えた割合は67%にのぼりました。このように、方言は完全に消滅するというより、標準語との混交により変質しながら徐々に薄まっていくというのが現実の姿なのです。
もう聞けない?各地の絶滅危惧方言リスト
「そいつぁどえらい話だ」「なんぼほど欲しいと言われても譲れんちゃ」——こんな言葉、最近聞いたことがありますか?日本各地には、いまや老年層でさえも使わなくなった「幻の方言」が数多く存在します。2022年に文化庁が行った調査によれば、伝統的方言の約37%が「絶滅危惧種」に分類され、地域の言葉の多様性が急速に失われていることが明らかになっています。ここでは、すでに姿を消しつつある地域別の方言表現をご紹介します。
東日本の消えゆく方言
東北地方の失われた表現
東北地方は日本で最も方言の多様性が保たれてきた地域ですが、それでも若年層ではほとんど使われなくなった表現が数多くあります。
青森県の消えゆく方言
- 「あづましねぇ」(落ち着かない、具合が悪い) ⇒ かつては体調不良から精神的な不安まで幅広く使われた表現でしたが、2018年の県立郷土資料館調査では、20代で使用率がわずか3%にまで低下。
- 「ぼるつかね」(役に立たない) ⇒ 「これはぼるつかねものだ」(これは役立たずだ)といった言い方で使われてきましたが、現在では70代以上の高齢者でさえ使用率が15%程度に。
岩手県の絶滅危惧方言
- 「かもがる」(面倒を見る、世話をする) ⇒ 「子どもをかもがる」のように使われてきた言葉ですが、現在では「面倒を見る」や「世話をする」という標準語に完全に置き換わっています。
岩手大学の佐藤教授による聞き取り調査(2020年)では、70歳以上の高齢者188人中62人が「かもがる」の意味を正確に答えられたのに対し、40代以下では217人中わずか3人しか意味を知らないという衝撃的な結果が出ています。
山形県の失われた表現
- 「あらまいね」(素晴らしい、驚くべきだ) ⇒ 「あいつの腕前はあらまいね」のように使われていた賛辞の言葉。現在では観光用の「方言グッズ」には残るものの、日常会話からは消滅しています。
関東・甲信越の忘れられた言葉
標準語の基盤となった関東地方でも、かつては豊かな方言が存在していました。特に周縁部や山間部には独特の言い回しが数多くありましたが、都市化と人口流動により急速に失われています。
茨城県の消えた方言
- 「じょっぺる」(捨てる) ⇒ 「そんなもん、じょっぺてしまえ」のように使われていましたが、現在60代以下ではほとんど使用されません。
- 「おっかない」(恥ずかしい) ⇒ 関東の一部で「恐ろしい」ではなく「恥ずかしい」の意味で使われてきた言葉。「人前で歌うのはおっかない」のように使われていましたが、現在では「恐ろしい」の意味との混同を避けるため、ほぼ消滅しています。

群馬県の絶滅危惧方言
- 「おぜんだい」(食事、ごはん) ⇒ 「おぜんだいの時間だよ」のように使われた表現。2019年の県教育委員会調査では、10代の認知率がわずか8%にとどまりました。
長野県の失われた表現
- 「おやげない」(もったいない) ⇒ 「そんな良いものを捨てるなんておやげない」のように使われていましたが、現在では「もったいない」に完全に置き換わっています。長野県方言保存会の記録によれば、1980年代には県内全域で広く使われていた表現が、わずか40年で消滅寸前になっています。
西日本の絶滅危惧方言
関西・中国地方の古い言い回し
関西弁は全国的に知名度が高く、比較的保存状態の良い方言ですが、それでも若年層では使わなくなった古い表現が少なくありません。
大阪府の消えつつある方言
- 「ほかす」(捨てる) ⇒ 「そんなもんほかしときや」のように使われていた言葉ですが、現在の若者の多くは「捨てる」や「ほる」を使います。大阪市立大学の調査(2017年)では、20代の使用率が7%にまで低下しています。
- 「しゃあない」に代わる「しゃあしゃあ」 ⇒ かつては「仕方がない」の意味で「しゃあしゃあ」という表現も使われていましたが、現在では「しゃあない」に一本化されています。
広島県の絶滅危惧方言
- 「ぶちええ」(とても良い) ⇒ 「ぶち」自体は広島弁として現役ですが、「ぶちええ」という組み合わせは若年層では「めっちゃええ」などに置き換わりつつあります。
- 「いご」(魚の卵、特にイクラ) ⇒ 「いごめし」(魚卵をのせた飯)などの料理名で残るものの、日常会話ではほぼ聞かれなくなった言葉です。
四国・九州の消えゆく方言
語彙も文法も標準語と大きく異なる九州の方言は、特に若年層で急速に失われています。
高知県の失われた表現
- 「ちくと」(少し) ⇒ 「ちくと待ちゅう」(少し待って)のように使われていましたが、現在では若年層の間で「ちょっと」に置き換わっています。高知大学の調査(2021年)では、10代の認知率が23%にまで低下しています。
熊本県の消えゆく方言
- 「ごつ」(とても) ⇒ 「ごつ疲れた」(とても疲れた)のように使われていましたが、若年層では「めっちゃ」などの全国共通語に置き換わりつつあります。
鹿児島県の絶滅危惧方言
- 「がんす」(〜します、〜いたします) ⇒ 「明日行きがんす」(明日行きます)のように使われる丁寧語。現在でも70代以上の高齢者の会話では聞かれますが、若年層ではほぼ消滅しています。
この他にも数多くの方言が消えつつありますが、地域の言葉が失われることは、その土地の文化や歴史、アイデンティティの一部が失われることでもあります。次の章では、そんな貴重な言葉を守るための取り組みについて見ていきましょう。
方言保存への取り組みと私たちにできること
「言葉は文化であり、歴史である」——これは言語学者によくいわれる言葉ですが、方言はまさに地域の風土や人々の暮らしの知恵が凝縮された文化遺産といえるでしょう。ユネスコは2009年に「消滅の危機にある言語」のリストを発表し、その中には琉球諸語(沖縄方言など)や八丈語(八丈島の方言)なども含まれています。方言の消滅は単なるコミュニケーション手段の変化ではなく、地域固有の文化や知恵の喪失を意味するのです。では、そんな貴重な言語資源を守るために、どのような取り組みが行われ、私たち一人ひとりに何ができるのでしょうか。
地域における方言保存活動
方言辞典と記録プロジェクト

失われゆく方言を記録に残す取り組みは、全国各地で行われています。その代表的な例をいくつか紹介しましょう。
「消えゆく方言を救え」プロジェクト(国立国語研究所) 2010年から始まったこのプロジェクトでは、全国47都道府県の方言を音声・映像・テキストで記録し、デジタルアーカイブとして保存しています。特に高齢者の自然な会話を収録し、若い世代でも閲覧できるようウェブ上で公開している点が画期的です。
このプロジェクトの責任者である田中教授は次のように語っています。 「方言は単なる言葉の違いではなく、その地域の自然環境や生活様式、価値観までも反映しています。例えば、雪国の方言には雪の状態を表す言葉が驚くほど多様にあります。そうした知恵や感性を記録することは、未来のための文化保存なのです」
地域の方言辞典編纂 地元の有志による方言辞典づくりも盛んです。例えば、島根県出雲地方では「出雲弁辞典」が地元の高校生と高齢者の協働で作成され、約2,000語の方言が収録されました。単に言葉を記録するだけでなく、その方言が使われる状況や背景にある文化も含めて記録している点が評価され、2018年には地域文化功労賞を受賞しています。
方言音声ライブラリー 鹿児島大学の「薩摩方言音声ライブラリー」のように、実際の発音や会話を音声データとして記録・保存するプロジェクトも増えています。これは特に音の特徴が独特な方言の保存に効果的で、文字だけでは伝わらないイントネーションやアクセントまでも後世に残すことができます。
教育現場での取り組み
学校教育の中で方言を取り入れる動きも広がっています。
方言教育のカリキュラム化 沖縄県では2000年代から「方言の日」を設け、学校教育の中で伝統的な琉球語を学ぶ時間を確保しています。宮古島の城辺小学校では月に一度の「方言タイム」があり、地元の高齢者を「方言先生」として招き、子どもたちに昔の言葉を教えています。
方言劇・方言スピーチコンテスト 秋田県の「方言劇コンクール」や鹿児島県の「薩摩弁大会」のように、子どもたちが方言を使って発表する機会を提供する取り組みも効果を上げています。こうした活動は単に言葉を学ぶだけでなく、自分のルーツや地域への誇りを育む効果もあります。
秋田県の方言研究家・佐藤さんはこう語っています。 「子どもたちは方言劇の練習を通じて、おじいちゃんおばあちゃんに積極的に話しかけるようになりました。『おばあちゃん、この言葉ってどう使うの?』と尋ねる姿は実に微笑ましい。方言が世代間の架け橋になっているんです」
大学での方言研究支援 東北大学や琉球大学などでは方言研究センターを設置し、若手研究者の育成や地域と連携した方言保存活動を支援しています。2021年には東北大学と宮城県内5つの高校が連携し、地元の方言を調査・記録するプロジェクトが始まりました。学術的な裏付けを持った保存活動は、単なる記録にとどまらない方言研究の発展にも貢献しています。
日常生活で方言を守るヒント
家庭でできる方言継承法

方言を守るために最も重要なのは、日常的に使うことです。家庭内でできる方言継承のアイデアをいくつか紹介します。
方言デーの設定 月に1回でも「方言デー」を設け、家族で意識的に方言を使う日を作ってみましょう。「今日は標準語禁止デー」として子どもたちと一緒に楽しむことで、方言への抵抗感を減らすことができます。
三世代会話の記録 祖父母・親・子の三世代で会話する様子をスマートフォンで録音・録画し、家族の言葉の記録を残してみましょう。後で聞き返すことで、自分の家庭ならではの言葉や表現に気づくきっかけになります。
方言カルタの作成 家族で使う方言を集めて、オリジナルの「方言カルタ」を作ってみるのも楽しい方法です。「あ」から始まる方言、「い」から始まる方言…と集めていくだけでも、思わぬ発見があるでしょう。
「方言ノート」の作成 子どもに「方言探偵」になってもらい、祖父母や近所の高齢者が使う珍しい言葉を記録する「方言ノート」をつけてもらうのも効果的です。学校の自由研究にもなり、子どもの探究心も刺激します。
SNSと方言復興の可能性
現代のテクノロジーは、方言保存の強力な味方にもなります。
SNSでの方言発信 TwitterやInstagramで「#〇〇弁」「#方言チャレンジ」などのハッシュタグをつけて投稿する若者が増えています。鹿児島の高校生グループ「薩摩弁普及委員会」は、TikTokで方言レッスン動画を公開し、全国から10万フォロワーを集める人気アカウントに成長しました。

方言ポッドキャスト 「津軽弁ラジオ」「京都べんラジオ」など、方言を使ったポッドキャスト配信も人気です。通勤・通学中に聴くことで、気軽に方言に触れる機会を作ることができます。
方言アプリの活用 「方言翻訳アプリ」や「方言学習アプリ」も増えています。秋田県が開発した「秋田弁ナビ」は、標準語と秋田弁を相互に翻訳できるだけでなく、音声で発音も聞くことができる便利なアプリです。観光客向けに作られたものですが、地元の若者にも好評で、ダウンロード数は5万を超えています。
方言オンラインコミュニティ 「津軽弁話者の会」「薩摩弁オンライン教室」など、オンラインで方言を学び合うコミュニティも生まれています。地元を離れた人でも参加できるため、Uターン・Iターン希望者の地域への愛着を育む効果も期待されています。
方言は単なる過去の遺物ではなく、地域のアイデンティティを形成する重要な文化資源です。完全に元の形で保存することは難しいかもしれませんが、次世代に何らかの形で継承していくことは、多様な日本文化を守ることにつながります。あなたの身近な方言、ぜひ大切にしてみませんか?
ピックアップ記事

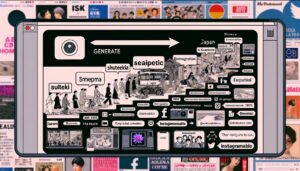



コメント