SNSの進化と共に消えていった「死語」の実態
スマートフォンを開けば、そこには常に新しい言葉があふれています。今日の流行語が、明日には「え、まだ使ってるの?」と言われてしまう——そんな言葉の移り変わりの速さは、特にSNSの世界で顕著です。
死語とは何か – インターネット用語の賞味期限
「死語」とは、かつて広く使われていたものの、現在ではほとんど使用されなくなった言葉や表現を指します。特にインターネット上では、この「言葉の賞味期限」が驚くほど短いのが特徴です。
リアルな会話での言葉の変化は比較的緩やかですが、SNSでの流行語は、まるでファッショントレンドのように、めまぐるしく変化します。国立国語研究所の調査によれば、インターネット上の流行語の平均寿命は約1.5〜2年程度と言われていますが、特に若年層が多く利用するプラットフォームでは、その期間がさらに短縮される傾向にあります。

死語になる主な要因:
- 使いすぎによる飽和状態
- 新しい言葉への置き換え
- 元ネタの風化
- プラットフォームそのものの衰退
SNSプラットフォームごとに異なる死語の傾向
興味深いことに、死語の発生と消滅のパターンは、SNSプラットフォームごとに特色があります。それぞれのプラットフォームが持つ特性や、主なユーザー層の違いがこの現象に影響しています。
Twitterで流行した死語の例
Twitterは文字数制限があるため、短く簡潔な表現が生まれやすい土壌です。
| 死語 | 流行時期 | 意味 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|
| 「なう」 | 2009〜2013年頃 | 現在〜している | ほぼ使用されず |
| 「わかる(わかりみ)」 | 2014〜2017年頃 | 共感する | 一部で残存 |
| 「FF外から失礼します」 | 2013〜2018年頃 | フォロワー外からの発言 | 揶揄される傾向 |
特に「なう」は、Twitter黎明期を象徴する言葉でしたが、今ではその使用は「おっさん認定」されるリスクすらあります(2023年SNSトレンド調査)。
Instagramで一時期人気だった表現
視覚的コンテンツが中心のInstagramでは、特有のハッシュタグ文化が発達し、独自の死語が形成されました。
- #インスタ映え — 2017年の流行語大賞にも選ばれましたが、現在では「インスタ映え狙い」というネガティブな文脈で使われることが多い
- #ぴえん — 悲しい表情を表す絵文字と共に爆発的に広まったが、過剰使用により急速に廃れた例
TikTokの短命な流行語
動画プラットフォームであるTikTokでは、音声と動きを伴う表現が流行するため、特に言葉のライフサイクルが短い傾向にあります。
TikTokでの超短命語彙の例:
- 「推し活」:アイドルやキャラクターを応援する活動
- 「よき」:良いという感情を表す
- 「エモい」:感情が揺さぶられる状態

これらの表現は、一時期爆発的に使用されましたが、過剰使用によって早々に「イタい」表現とされ、Z世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)の間ではすでに使用が減少しています。
死語になる速度が加速する現象とその背景
デジタルコミュニケーション研究者の間では、「言語進化の加速化現象」として注目されていますが、なぜSNS上の言葉の寿命はこれほどまでに短くなっているのでしょうか?
- 情報伝達速度の飛躍的向上:かつては地域や集団内で徐々に広まっていた新語も、現在ではわずか数時間で全国に拡散
- コンテンツの過剰供給:毎日膨大な量の投稿が行われ、新鮮さを保つ期間が短縮
- 差別化への欲求:特に若年層は、主流から少し外れた表現を好む傾向がある
また、企業のマーケティングが若者言葉を取り入れることで、その言葉の「死語化」が促進されるという皮肉な現象も見られます。一度企業の公式アカウントやCMで使われた言葉は、たちまち「おっさん言葉」のレッテルを貼られてしまうのです。
流行り言葉がこれほど早く生まれては消えていく現代のSNS環境は、言語研究者にとっても興味深い研究対象となっています。次の章では、特に2010年代前半に流行したSNS死語にフォーカスして、その栄枯盛衰を見ていきましょう。
懐かしい!2010年代前半に流行したSNS死語ベスト10
スマートフォンとSNSが日本でも急速に普及し始めた2010年代前半。この時期は、独特のネット言葉が次々と生まれては消えていった、言語学的に見ても非常に興味深い時代でした。当時SNSを使っていた方なら「あぁ、懐かしい!」と思わず笑みがこぼれる言葉の数々を振り返ってみましょう。
スマホ初期時代を彩った若者言葉
2010年代前半は、ガラケーからスマホへの移行期であり、Twitter、Facebook、LINEなどのSNSが急速に普及した時期と重なります。この時代に生まれた言葉は、デジタルネイティブ世代の文化を色濃く反映していました。
「なう」「なう」を使った派生語
「なう」は、英語の「now(今)」を音写した言葉で、Twitter黎明期を象徴する表現です。2009年頃から使われ始め、2012年頃に最盛期を迎えました。
「なう」の使用例:
- 「渋谷なう」(現在渋谷にいる)
- 「勉強なう」(今勉強している)
- 「電車なう」(今電車に乗っている)
さらに派生形として、「なう」を複合的に使った表現も次々と生まれました。
- 「なうぷれ」:今プレイしている音楽
- 「なうみん」:今寝ている
- 「帰宅なう」:今帰宅した
2013年に行われたWeb調査(インターネット言語文化研究所調べ)によれば、「なう」の使用率は10代〜20代の若年層で約78%に達していましたが、2023年の同様の調査では、使用率はわずか5%程度にまで低下しています。現在では「なう」を使うことは「おっさん認定」の対象となり、若者の間では避けられる傾向にあります。
「ワンチャン」「そだねー」の変遷
「ワンチャン」は「ワンチャンス」の略で、「もしかしたら可能性がある」という意味で使われました。2012年頃から流行し、特に若い男性の間で爆発的に広まりました。

使用例:
- 「明日ワンチャン雨かも」
- 「ワンチャンあるで!」
一方、「そだねー」は2018年平昌オリンピックの女子カーリングチーム「LS北見」の選手たちが試合中に頻繁に使用していたことから一気に脚光を浴び、2018年の流行語大賞に選ばれました。しかし、あまりにも多用されたため、わずか1年足らずでネット上では「使うと恥ずかしい言葉」となってしまいました。
ネットミームから生まれた一時的流行語
SNS上では、特定の出来事やコンテンツから派生した「ミーム(文化的遺伝子)」が短期間で広まり、そして消えていくことがよくあります。
「あけおめことよろ」の衰退
年始の挨拶として「あけましておめでとう、ことしもよろしく」を略した「あけおめことよろ」は、文字数制限のあるTwitterや、手軽に送れるLINEの普及と共に広まりました。2010年〜2014年頃に最も流行しましたが、簡略化しすぎることへの反発や、より新しい省略表現(「あけおめ」だけにするなど)の登場により、次第に使用頻度が減少していきました。
総務省情報通信政策研究所の調査によれば、2015年には20代の約65%が年始の挨拶で「あけおめことよろ」を使用していましたが、2023年には同世代で使用率は10%以下に低下しています。
「オワコン」の皮肉な運命
「終わったコンテンツ」を意味する「オワコン」は、2010年代前半にネット上でよく使われた言葉です。主に人気が下降したゲームや漫画、アイドルなどを皮肉る際に使用されました。
使用例:
- 「あのゲームはもうオワコン」
- 「AKBはオワコン」
しかし皮肉なことに、「オワコン」という言葉自体が時代遅れとなり、今では「オワコン」と言う表現自体が「オワコン」になっています。2023年のSNS言語トレンド調査では、10代の約90%が「『オワコン』という言葉を日常的に使わない」と回答しています。
企業マーケティングが作り出した死語たち
企業がマーケティング活動の一環として流行語を取り入れたり、自ら作り出そうとしたりすることがありますが、そうした言葉は特に「死語化」しやすい傾向にあります。
企業主導で生まれた死語の例:
- 「ググる」:Google で検索することを意味する動詞。現在では「調べる」「検索する」という一般的な表現に戻りつつある
- 「RT希望」:リツイート(拡散)を求める表現。現在では「拡散希望」や単に「#拡散」というハッシュタグに置き換わっている
- 「それな」:共感を表す表現で、数多くの企業広告に採用された結果、若者の間で急速に使用率が低下

企業公式アカウントによる若者言葉の使用については、ブランドイメージ研究所が興味深い調査結果を発表しています。企業が若者言葉を使うと、その言葉の「若者言葉としての寿命」は平均で約40%短くなるというデータがあるのです。
2010年代前半に大流行したSNS用語の多くは、今では「懐かしのネット言葉」としてネタ的に使われることはあっても、真面目な文脈で使用されることはほとんどありません。次の章では、こうした死語をうっかり使ってしまうリスクと、現代のSNSコミュニケーションで気をつけるべきポイントについて見ていきましょう。
死語を使ってしまうリスクと現代のSNSコミュニケーション術
SNSでの会話は、リアルな対面コミュニケーションと異なり、書き言葉だけで相手に印象を与えます。そのため、使う言葉一つで「時代遅れな人」と判断されてしまうリスクがあるのです。では、なぜ死語を使うことがリスクとなるのか、そして現代のSNSで適切にコミュニケーションを取るにはどうすればよいのでしょうか。
「おっさん認定」されるSNS上の言動パターン
SNS上で「おっさん認定」されるというのは、若い世代から「時代に取り残された古い感覚の人」と見なされることを指します。特に、若者が多く利用するプラットフォームでは、こうした「世代間ギャップ」が顕著に表れます。
年齢がバレる死語の使い方
死語を使うことは、そのまま自分の年齢や世代を露呈してしまうことがあります。メディア研究者の鈴木清士氏によれば、「使用する言葉と流行時期の関係から、ユーザーの年齢層が±3歳の精度で推測可能」とのことです。
年代別に見る”致命的な死語”:
| 世代 | 使うと年齢がバレる死語 | 現在の若者の反応 |
|---|---|---|
| 40代以上 | 「うp」「ぁゃιぃ」「(^_^;)」 | 「謎の暗号?」と困惑 |
| 30代 | 「なう」「wktk」「orz」 | 「懐かしい!」と笑われる |
| 20代後半 | 「それな」「わかりみ」「推しが尊い」 | 若干の引き気味の反応 |
特に注意すべきは、過去に使われていた顔文字や記号の組み合わせです。「m(_ )m」や「(^^;)」などの古い顔文字は、現在の10代〜20代前半からは「なぜわざわざ文字で顔を作るのか」と不思議がられることもあります。
避けるべき典型的な”おっさん言動”:
- 連続した顔文字の使用:「(^^)/(^^)/(^^)/」
- 過剰な省略:「おはよう」→「おは」(現在では違和感)
- 時代遅れのネットスラング:「ぐぬぬ」「ノシ」「キボンヌ」など
プラットフォームごとの世代間ギャップ
各SNSプラットフォームには、主要ユーザー層があり、その中で「標準的」とされる言葉遣いが存在します。プラットフォームごとの特性を理解せずに投稿すると、思わぬ反応を引き起こす可能性があります。
プラットフォームごとの世代と言語の特徴:
- Twitter:幅広い年齢層が利用。ただし、ハッシュタグの使い方や略語の選択で世代差が出やすい
- Instagram:写真中心でテキストは少なめ。絵文字の使い方に世代間ギャップが表れやすい
- TikTok:若年層中心。最新の言葉が生まれる場でもあり、古い表現が最も忌避される
- Facebook:比較的年齢層が高い。若者言葉の使用自体が違和感を生じることも
国内の大手SNSマーケティング会社の調査によれば、「プラットフォームごとに適した言葉遣いができているユーザー」は、フォロワー獲得率が平均して1.8倍高いという結果も出ています。
若者言葉を追いかけるべきか – 適切な言葉選びのコツ

では、「おっさん認定」を避けるために、常に最新の若者言葉を取り入れるべきなのでしょうか?答えは「NO」です。無理に若者言葉を使おうとすることは、かえって不自然さを生み、「痛い」印象を与える可能性があります。
自然な会話を心がけるためのポイント
SNSでの効果的なコミュニケーションのためには、以下のポイントを意識するとよいでしょう。
❶ 自分らしさを保つ
- 無理に若者言葉を使わない
- 自分の世代の言葉を恥じない
- ただし、明らかな死語は避ける
❷ コンテキストに合わせる
- ビジネス目的の投稿と個人的な投稿で言葉遣いを使い分ける
- 投稿するプラットフォームの特性を理解する
- 会話の流れに自然に合わせる
❸ 観察と学習を怠らない
- 一方的に発信するだけでなく、他者の投稿から学ぶ
- トレンドワードの使われ方を観察する
- 自分の投稿に対する反応をフィードバックとして活用する
コミュニケーションコンサルタントの田中真理氏は、「SNSでの言葉選びは、年齢を隠すためではなく、相手に敬意を示し、効果的にコミュニケーションを取るためのもの」と指摘しています。無理に若作りするよりも、相手と自然につながることを目指しましょう。
流行に左右されない、長く使える表現技法
SNSの流行語は移り変わりが激しいですが、いつの時代も通用する表現技法もあります。これらをマスターすれば、「死語警察」を気にせず、自分らしい発信を続けることができるでしょう。

時代を超えて使える表現のコツ:
- 具体的な描写:抽象的な表現より、具体的な描写の方が共感を得やすく、時代を超えて伝わりやすい
- 率直さ:過度に飾らない正直な感想は、どの世代からも好意的に受け取られやすい
- ユーモア:自虐や軽いジョークは、世代を超えて共感を呼びやすい(ただし、センシティブな話題には注意)
- 敬意と礼儀:基本的な礼儀を守った言葉遣いは、どの世代にも通用する
また、最新の言葉を取り入れたいときは、以下の3つの「様子見ルール」を意識すると失敗を避けられます。
新しい言葉を取り入れる際の「様子見ルール」:
- その言葉がSNS上でどのように使われているか、十分に観察する
- 一般的になってから少なくとも3ヶ月は様子を見る
- 最初は控えめに使い、反応を見てから本格的に取り入れる
SNSは自己表現の場であり、世代間のコミュニケーションの架け橋でもあります。死語を恐れるあまり萎縮するのではなく、自分らしさを保ちながら、相手に敬意を示す言葉選びを心がけることが、長期的には最も効果的なSNSコミュニケーション術と言えるでしょう。
ピックアップ記事


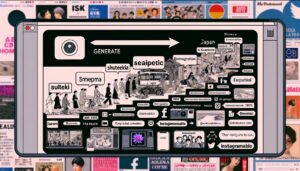


コメント